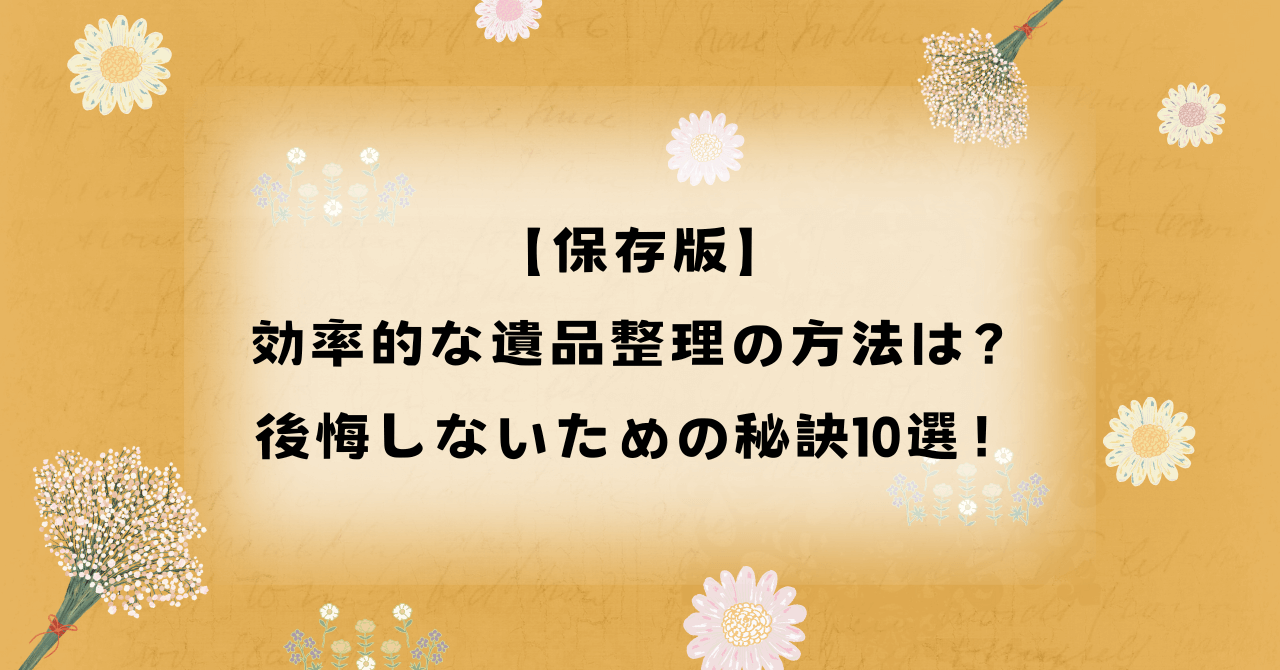親の家の遺品整理、一人じゃ大変そう…。



どこから手を付けていいか分からないよね
遺品整理の効率的に進めるにはどうすれば良いのでしょうか。
遺品整理方法や、効率的な進め方が知りたいですよね。
この記事では、遺品整理の基本的な進め方と、スムーズに進めるための秘訣10選、さらに遺品整理業者の選び方について紹介していきます。
- 遺品整理を始める前の準備ステップ
- 遺品整理の基本的な進め方
- 遺品整理を効率よく進める秘訣10選
遺品整理を始める前の準備


遺品整理を円滑に進めるには、事前の準備が欠かせません。
整理方針を関係者と共有し、整理範囲や期間を明確にしておくことで、作業がスムーズになります。
ここでは、以下の3つのポイントについて解説していきます。
事前準備を万全にすることで、本格的な遺品整理作業がグッとラクになりますよ。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
家族や関係者と整理方針を話し合う
遺品整理を始める前に、まずは家族や関係者と整理方針について話し合うことが大切です。
亡くなった方との思い出や、残された品物に対する感情は人それぞれですから、関係者の意見を聞いて調整していく必要があります。
話し合いのポイントは以下の3つです。
- 遺品の取捨選択の基準を決める
- 思い出の品の分配方法を検討する
- 処分する品物の具体的な方法を話し合う
特に、思い出の品の扱いは人によって意見が分かれやすいところです。
誰かの思い入れが強いものは、その人の元へ優先的に渡すなどのルールを決めておくと良いでしょう。
また、処分品の具体的な方法(寄付、売却、廃棄など)も事前に取り決めておくことで、作業がスムーズになります。
話し合いの際は、故人を偲びつつ、前向きな雰囲気を心がけることが大切ですね。
遺品整理は、故人との最後のお別れの作業だと思えば、自然と丁寧に取り組めるはずです。



家族みんなで故人を偲びながら整理できるのが理想ですね
遺品整理の範囲と期間を決める
遺品整理を始める前に、整理の範囲と期間を明確にしておくことが重要です。
漠然と「全部片付ける」と考えていると、作業が思ったより大変だと感じてしまうかもしれません。
整理範囲を決めるポイントは、以下の3つです。
- 故人の生活スペースを中心に整理する
- 共有スペースは必要最小限の整理にとどめる
- 思い出の詰まった場所は優先的に整理する
故人の部屋や使っていた家具などを中心に、段階的に整理範囲を広げていくのが良いでしょう。
最初から広範囲の整理を考えすぎると、体力的にも精神的にもキツくなってしまいます。
整理にかける期間も、家族の予定や心の準備を考慮して無理のない計画を立てましょう。
急ぐ必要はありません。
1週間や1ヶ月など、区切りの良い期間を設定して、少しずつ整理を進めていくのがオススメです。
必要な道具や資材を揃える
遺品整理を効率的に進めるには、事前に必要な道具や資材を揃えておくことが大切です。
整理作業を始める前に、以下のようなアイテムを用意しておきましょう。
遺品整理に役立つ道具・資材リスト
- 軍手、マスク、エプロンなどの防護具
- ダンボール箱、収納ボックス
- ガムテープ、マジック、はさみ
- ゴミ袋(可燃、不燃、粗大ごみ用)
- デジタルカメラ、メモ帳
特に、ダンボール箱や収納ボックスは予想以上に必要になることが多いので、十分な量を用意するのがポイントです。
不用品の処分にはゴミ袋が欠かせませんし、大切な思い出は写真に残しておくと良いでしょう。
大量の遺品を前にすると、つい片付けたい一心で整理を始めてしまいがちです。
しかし、事前の道具の準備は、整理作業の効率アップに直結します。
必要なものをリストアップして、揃えておくことで、本格的な整理作業をスムーズにスタートできますよ。



準備8割が作業の効率を左右します
遺品整理の基本的な進め方


準備が整ったら、いよいよ遺品整理の作業に入ります。
とはいえ、いきなり全てを片付けようとしても、なかなか上手くいきません。
ここでは、以下の4つのステップで進めていくのがオススメです。
基本的な流れを押さえておけば、効率的に整理を進められるはずです。
それでは、一つひとつ解説していきましょう。
部屋ごとに区分けして整理する
遺品整理は、部屋ごとに区分けして進めていくのが基本です。
一つの部屋に的を絞ることで、作業の見通しが立てやすくなります。
部屋を区分けするポイントは、以下の3つです。
- 故人の生活感の強い部屋から着手する
- 寝室、リビング、キッチンなど、部屋の用途で区分けする
- 思い出の詰まった部屋を優先的に整理する
故人の遺品が多く残っている部屋から着手することで、整理作業の達成感を得られます。
寝室やリビングなど、生活感の強い部屋の整理は、故人の人となりを偲ぶ良い機会にもなるでしょう。
部屋ごとの整理が一段落したら、キッチンや洗面所など、共有スペースの整理に移るのがオススメです。
思い出の詰まった部屋は、最後に整理するのも一つの方法です。
思い出が強すぎると、つい整理が進まなくなってしまうことがあります。
思い出の品は後回しにして、まずは比較的整理しやすい部屋から着手するのが効率的ですよ。
思い出の品と処分する品に分ける
部屋ごとの整理が進んだら、次は遺品を「思い出の品」と「処分する品」に分類していきます。
遺品の取捨選択は、遺品整理の中でも特に重要なプロセスです。
ここで意識したいポイントが3つあります。
- 思い出の品は、厳選して残す
- 実用品は、今後使う予定があるか見極める
- 迷ったら処分する、を基本に考える
どんなに大切な思い出でも、全てを残すことはできません。
思い出の品は、本当に心に残るものだけを厳選して残すようにしましょう。
日用品などの実用品は、今後使う予定があるかどうかがポイントです。
「いつか使うかも」と考えても、ほとんどの場合は使わずに終わってしまいます。
処分に迷ったら「処分する」を選ぶ勇気も必要です。
大切な書類や貴重品は別保管する
遺品の中には、重要な書類や貴重品が含まれていることがあります。
これらは整理の際に紛失しないよう、一般の遺品とは別に保管しておくのがおすすめです。
具体的には、以下のようなものが該当します。
- 預金通帳、印鑑、権利書など
- 健康保険証、年金手帳などの公的書類
- アクセサリーや貴金属などの高価な品
書類は種類ごとにファイリングして、金庫や鍵付きの引き出しに保管するのが良いでしょう。
貴重品も、鍵のかかる安全な場所に保管することが大切です。
遺産分割の際に必要になることもあるので、整理が一段落するまでは処分せずに取っておくことをオススメします。
処分品は寄付・売却・廃棄に振り分ける
処分すると決めた遺品は、最終的に「寄付」「売却」「廃棄」の3つに振り分けます。
故人の遺志を汲んで、できるだけ多くの品物を寄付や売却するのが理想的ですね。
具体的な処分方法は、以下の通りです。
- 寄付:NPOや社会福祉協議会などに連絡する
- 売却:リサイクルショップやオークションを利用する
- 廃棄:市区町村の規定に従って適切に処分する
寄付は、着なくなった衣類や日用品などを中心に検討しましょう。
売却は、価値のありそうな品物を選んで、買取サービスなども活用すると良いですね。
廃棄は、処分業者へ依頼するなど、ルールに則った方法で行うことが肝心です。
故人の遺品を大切に扱いながら、適切な処分方法を選んでいきましょう。



できるだけ寄付や売却で、大切に処分したいですね
遺品整理をスムーズに進める秘訣10選
ここからは、遺品整理を効率的に進めるための秘訣を10個ご紹介します。
整理作業で行き詰まったときの「困った!」を解消する工夫が満載ですよ。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
秘訣1. 整理前に写真を撮っておく
整理を始める前に、故人の部屋や遺品の写真を撮っておくことをオススメします。
写真は、整理後に思い出を振り返るときに役立ちます。
遺品の全体像を記録しておけば、分配の参考にもなるはずです。
秘訣2. 思い出話をしながら整理する
遺品整理は、家族で協力しながら進めるのが理想的です。
整理の合間に、遺品にまつわる思い出話を振り返ってみるのも良いでしょう。
亡き人を偲び、家族の絆を深める機会にもなります。
秘訣3. 必要以上に取っておかない
思い出の品は、厳選して残すことが大切です。
「もしかしたら必要かも」と考えて、つい多くの品物を取っておきたくなるもの。
でも、必要以上に物を残してしまうと、整理がいつまでも終わりません。
思い切って手放すことも、立派な供養になるのです。
秘訣4. 大型家具から処分する
部屋の印象を変えるためには、大型家具から処分するのが効果的です。
タンスや本棚を処分するだけで、一気に部屋が片付きます。
大型家具を処分することで、整理のペースがグッと上がるはずです。
秘訣5. 衣類は季節ごとにまとめる
遺品の中でも衣類は量が多く、整理に時間がかかりがちです。
衣類は、まず夏物・冬物など季節ごとに分けるのがオススメです。
アイテム別(シャツ、パンツなど)に分類するのも効率的ですよ。
秘訣6. 書籍は得意分野ごとに分類する
故人の蔵書は、整理が難しいと感じる方も多いはず。
大量の書籍は、まずジャンルや得意分野ごとに分類するのがコツです。
思い入れの強い分野の本は残し、あとは思い切って処分するのがオススメです。
秘訣7. 思い出の品は保管方法を工夫する
アルバムや思い出の品は、保管場所と方法を工夫しましょう。
たとえば、アルバムはデータ化してクラウド上に保存するのも一案。
思い出の品は、風通しの良い場所で湿気対策をして保管することが大切です。
秘訣8. 定期的に休憩を取る
遺品整理は気が遠くなるような作業の連続です。
作業を効率的に進めるには、こまめな休憩が欠かせません。
1時間に10分程度の休憩を取り入れるなど、メリハリをつけるのがオススメですよ。
秘訣9. 完璧を目指さない
遺品整理で完璧を目指そうとすると、いつまでたっても作業が終わりません。
思い出に浸りすぎず、割り切ることも必要です。
「これでよし」と腹をくくることで、整理作業に区切りをつけやすくなりますよ。
秘訣10. 専門家に相談する
遺品整理は、一人で抱え込まずに専門家に相談するのも一つの手です。
士業や遺品整理業者などのプロに依頼すれば、適切なアドバイスがもらえるはず。
特に法的トラブルが心配な場合は、弁護士への相談をオススメします。



プロに頼ることで、自分の心にも余裕ができそうですね
遺品整理業者の選び方


遺品整理は自分たちだけで行うのが難しい場合、専門の業者に依頼するのも一つの選択肢です。
ただし、遺品整理業者を選ぶ際は慎重になる必要があります。
ここでは、信頼できる業者を選ぶためのポイントを3つご紹介します。
サービス内容と料金体系を比較する
まずは、複数の業者のサービス内容と料金体系を比較することから始めましょう。
遺品整理の料金は業者によってピンキリなので、事前の比較検討が欠かせません。
サービス内容も、業者ごとに異なります。
以下のような点をチェックしておくと良いでしょう。
- 遺品の整理・仕分けから処分までの一貫対応か
- 遺品買取サービスの有無
- 分類作業の料金は時間制か、箱単位の料金制か
サービス内容と料金体系を照らし合わせて、自分たちに合った業者を選ぶことが大切です。
遺品整理士の有無を確認する
次に確認したいのが、遺品整理士の有無です。
遺品整理士とは、一般社団法人遺品整理認定協会が認定する民間資格。
士業と連携して、円滑な遺品整理をサポートしてくれます。
以下のような観点から、業者の信頼性を判断できるでしょう。
- 遺品整理士の人数は十分か
- 遺品整理士の経験や実績は豊富か
- スタッフの教育体制は整っているか
特に、遺品整理の専門知識を持ったスタッフの厚みは重要です。
認定資格の有無は、業者選びの大きな判断材料になるはずです。
実績と評判をチェックする
最後は、業者の実績と評判をしっかりチェックしましょう。
ホームページやブログで、過去の遺品整理の事例を確認するのがおすすめです。
以下のような点に着目すると、業者の腕前が見えてきます。
- 遺品整理の実績件数は十分か
- ビフォーアフター写真で、整理の質が高いか
- 依頼主の満足度は高いか
ネット上の口コミや評判も、業者の選定に役立ちます。
依頼主の生の声を参考にしながら、信頼できる業者を見極めることが肝心です。
まとめ
この記事では、遺品整理の基本的な進め方と、スムーズに進めるための秘訣10選、さらに遺品整理業者の選び方について紹介してきました。
- 家族と整理方針を話し合って準備
- 思い出の品と処分品に分けて整理
- 専門家に相談しながら進めるのも◎
遺品整理は、物理的にも精神的にも大変な作業です。
ただ、故人との思い出に浸りながら、感謝の気持ちを込めて整理を進めていけば、必ず最後まで乗り越えられるはず。
整理のコツをしっかり押さえて、一つずつ着実に作業を進めていきましょう。



遺品整理は終活の大事な準備だと実感したわ。秘訣を参考にして、前向きに取り組んでいきたいと思ったわ
思い出の品は厳選して残し、処分する品は故人への感謝を胸に手放す。
遺品を通して、亡き人の想いを受け継いでいく。
それが、故人に対する最高の供養になるのだと思います。
この記事が、遺品整理に悩む方の道しるべとなれば幸いです。