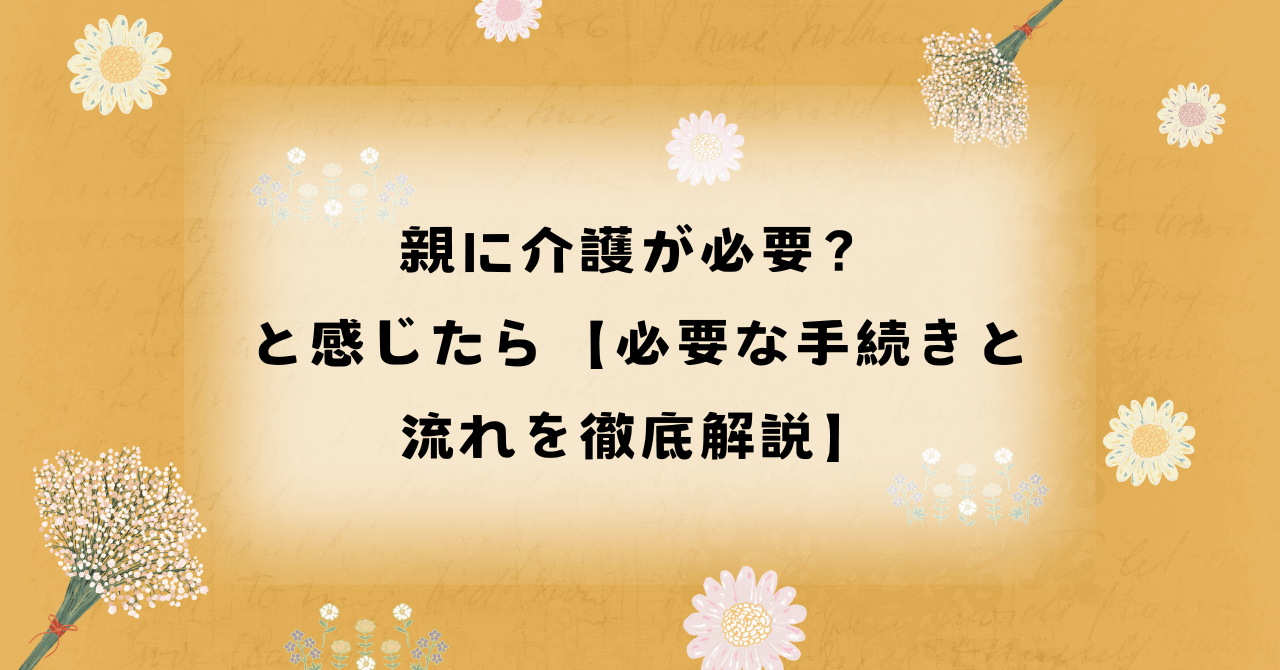親の介護は多くの人に関わりのある問題です。
しかし、親が元気な時には何故かあまり意識しませんよね?
親に介護が必要になって初めて必要な手続きや、その流れがわからないと困ってしまうようなことも少なくないと思います。
この記事では、親に介護が必要だと感じた時にするべき手続きと流れについて徹底解説していきます。
親の介護に必要な手続きと流れ

親に介護が必要となり介護サービスを受けたいと思っても、まずは手続きが必要です。
介護サービスを受けるまでに、何が必要かを解説していきます。
介護サービスを受けるまでの流れ
- 市町村の役所・地域包括支援センターで相談、要介護認定の申請をする
- 要介護認定を受ける
- 必要な介護サービスを決める
- ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼する
- 介護サービス事業者と契約し利用を開始する
市町村の役所・地域包括支援センターで相談、要介護認定の申請をする
市町村の役所の高齢者福祉窓口、または地域包括支援センターで必要書類を揃え要介護認定の申請をします。
要介護認定に必要な書類
- 申請書
- 介護保険の被保険者証
- 健康保険の保険証(65歳以下の場合)
申請は原則として本人か家族が行いますが、難しい場合は代行申請の制度もあります。
要介護認定を受ける
認定調査員が家庭を訪問し、どの程度の介護が必要なのか調査します。
時間は1時間程度で費用は無料です。
利用対象者と話し、心身の状態・生活環境・日常生活・身体的問題について聞き取りをします。
認定調査後、調査員が持ち帰った情報をもとに、コンピュータで全国一律に解析された結果の1次判定。
次に主治医の意見書を提出し、専門家によって構成される介護認定審査会で2次判定。
要介護認定の申請から約30日程度で認定結果が届きます。
- 利用開始は申請日まで遡って設定されるので、申請から結果通知までの期間に利用したサービスも保険給付の対象です。
- 介護認定の結果にはそれぞれ有効期限があります。
- 介護認定の満了前までに新規申請と同じ更新申請を行わず、有効期間を過ぎてしまうと利用ができなくなってしまうので要注意です。
必要な介護サービスを決める
要介護認定の結果次第で利用できるサービスが異なります。
市町村の役所、地域包括支援センターで相談し、どのようなサービスの利用が出来るのか確認しましょう。
非該当(自立)
介護サービスは受けられません。
審査に納得が出来ない場合は、認定結果に対する異議申し立てをします。
また、非該当となった場合でも市町村が提供するサービスや民間のサービスを利用し介護負担を軽減させることは出来ます。
介護予防・生活支援サービス事業
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- その他の生活支援サービスなど
一般介護予防事業(全ての高齢者が利用可なもの)
- 介護予防普及啓発事業
- 地域介護予防活動支援事業
- 地域リハビリテーション活動支援事業など
要支援1・2
要介護1・2で利用できるのは【介護予防サービス】です。
介護予防サービスは『状態が悪化して要介護になることを防ぐ』という目的があります。
| 支給限度額/月 | 利用出来るサービス | |
| 要支援1 | 50,030円 【自己負担額】 1割:5,003円 2割:10,006円 | 介護予防サービス ・介護予防訪問看護 ・介護予防通所リハビリ ・介護予防居宅療養管理指導など 地域密着型介護予防サービス ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型通所介護など |
| 要支援2 | 104,730円 【自己負担額】 1割:10.473円 2割:20,946円 |
要介護1~5
| 支給限度額/月 | 利用出来るサービス | |
| 要介護1 | 166,920円 【自己負担額】 1割:16,692円 2割:33,384円 | 施設サービス ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 居宅サービス ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・短期入所など 地域密着型サービス ・定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護 ・小規模多機能型居宅介護 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型共同生活介護など |
| 要介護2 | 196,160円 【自己負担額】 1割:19,616円 2割:39,232円 | |
| 要介護3 | 269,310円 【自己負担額】 1割:26,931円 2割:53,862円 | |
| 要介護4 | 308,060円 【自己負担額】 1割:30,806円 2割:61,612円 | |
| 要介護5 | 360,650円 【自己負担額】 1割:36,065円 2割:72,130円 |
ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼する
介護サービスを利用するにはケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。
ケアプラン:利用者が介護保険サービスを使うための計画書
ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼しましょう。
- 要支援1~2:ケアプランは、地域包括支援センターで作成を依頼することができます。
- 要介護1~5
- 在宅サービスの利用→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)にケアプランを作成してもらう。
- 施設サービスの利用→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
介護サービス事業者と契約し利用を開始する
作成したケアプランをもとに、実際に介護サービス事業者と契約します。
契約に必要な書類は、「契約書」「サービス内容説明書」「重要事項説明書」の3種類です。
すべてに名前を自筆で記載し、印鑑を押します。
介護サービス事業所と契約後、介護サービスの利用が開始されます。
まとめ
この記事では、親に介護が必要だと感じた時にするべき手続きと流れについて解説してきました。
介護が必要かな?と思ったらなるべく早く動くことをおススメします。
- 市町村の役所・地域包括支援センターにまず相談しましょう
- 要介護認定を受けましょう
- ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼しましょう
相談して、頼り、使えるサービスはしっかり使うということが大切です。