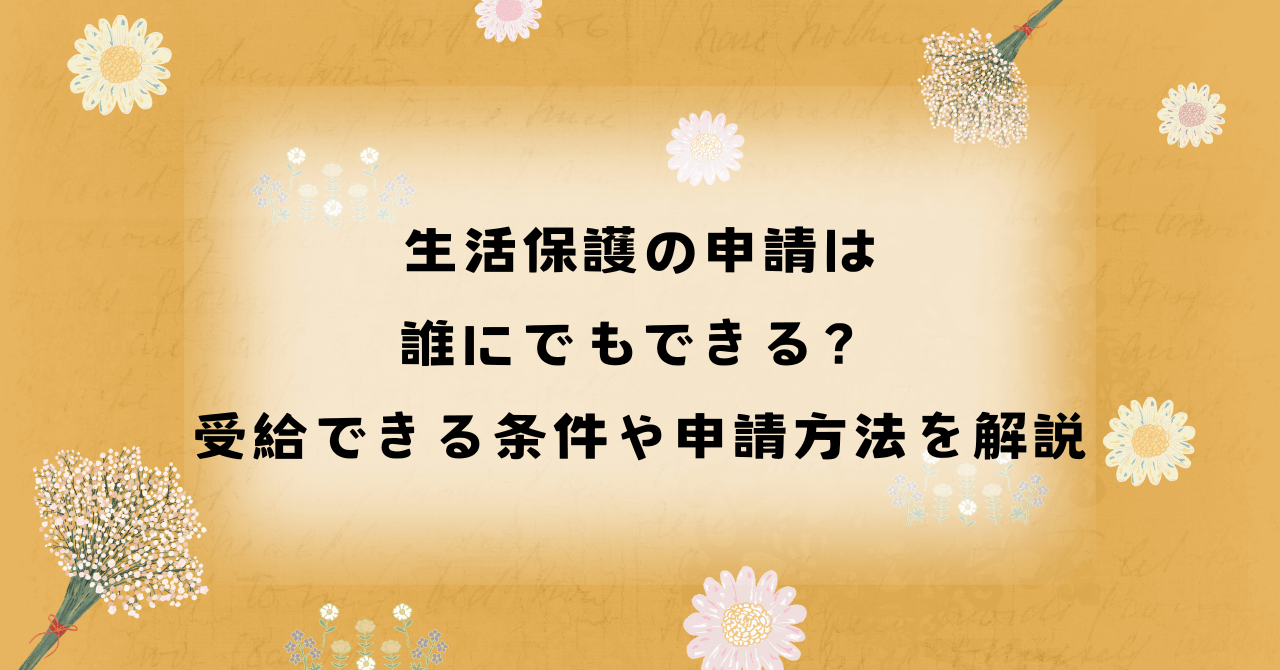生活保護は他人事だと思っていた人も多いのではないでしょうか?
私も、実父の生活を知るまでは正直どこか他人事だと思っていました。
しかし、この不安定な世の中で生活保護は命を守る大切な制度です。
生活保護は誰でも申請できる?
受給できる条件や申請方法が分からないという人も多いと思います。
この記事では、生活保護の申請は誰にでもできるのか?受給できる基準や申請方法について詳しく解説していきます。
生活保護の申請は誰にでもできるって本当?

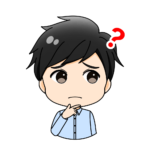
生活保護は誰でも申請できるの?



できますよ!
生活保護の申請は誰でもできるものなのでしょうか?
申請をする権利は日本国民全員にあります。
生活保護は【最低限度の生活を保障する】日本国民の権利です。
必要な状態になった時には、生活保護の制度を利用しましょう。
生活保護制度とは?
生活保護は、国が国民の【健康で文化的な生活を保証する】制度のことです。
扶助は8種類に分けられ、その中から要受給者に必要な扶助が支給されます。
- 生活扶助
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など) - 教育扶助
義務教育を受けるために必要な学用品費 - 住宅扶助
アパートなどの家賃 - 医療扶助
医療サービスの費用 - 介護扶助
介護サービスの費用 - 出産扶助
出産費用 - 正業扶助
就労に必要な技能の修得等にかかる費用(技能習得費・就職支度費など) - 葬祭扶助
葬祭費用
生活保護を受給できる条件
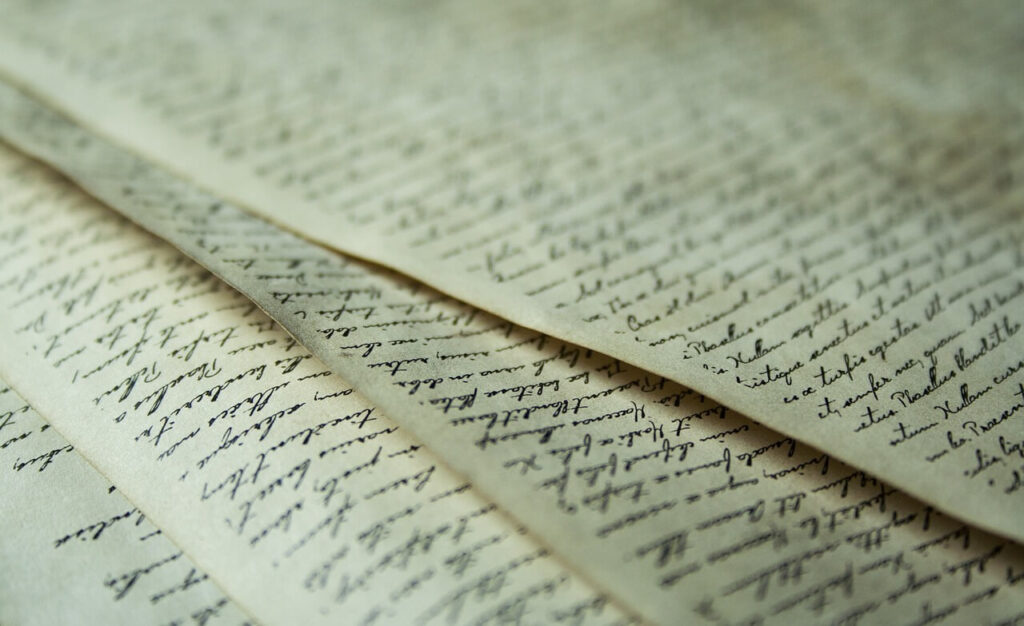
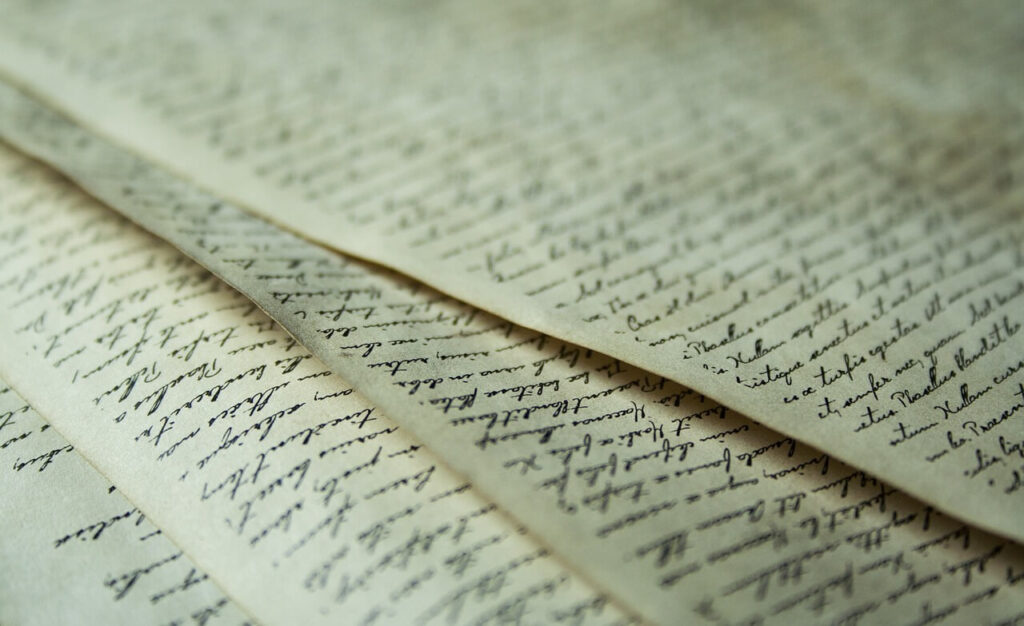
生活保護を受けるために条件はあるのでしょうか?
収入が最低生活費に満たない+4つの条件があります。
日本国民であれば全ての人が申請する事の出来る生活保護ですが、実際に受給出来るのは収入が厚生労働省が定める「最低生活費」に満たず4つの条件に当てはまる人です。
*厚生労働省:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和2年10月)
生活保護受給までの4つの条件
4つの条件とはどのようなものでしょうか?
- 資産の活用
- 能力の活用
- あらゆるものの活用
- 扶養義務者の扶養
資産の活用
預貯金や土地、家屋など資産になるものは売却するなどして生活費に充てなければなりません。
しかし、例外的に不動産や自動車など売っても資産にならない、または仕事するためにどうしても必要な場合など保有が認められることもあります。
能力の活用
働くことが可能な状態であれば労働しなければなりません。
あらゆるものの活用
他の社会保障制度(年金や手当)など生活保護の他に活用できるものがある場合はそちらを優先します。
扶養義務者の扶養
扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹)からの援助が可能である場合は、援助を受けなければなりません。
生活保護はどれくらい支給される?
生活保護費はどのくらいの金額が支給されるのでしょうか?
厚生労働省が定める最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます。
働いていたり、年金を受給している場合であっても条件に当てはまる場合は生活保護を受給できます。
生活保護の申請方法から受給までの流れ


生活保護の申請方法、受給までの流れを解説します。
まずは、居住地域の福祉事務所の生活保護課の窓口に行き「生活保護の申請がしたい」と申し出ましょう。
生活保護担当の職員との面談(相談)があり、生活状況や家庭状況を詳しく聞かれます。
その際、生活保護以外の選択肢を強く勧められることがありますが、本当に生活保護が必要な場合は引き下がらず申請用紙をお願いしましょう。
生活保護の受給までに大切なのは生活保護を受ける本人の強い意志です。
生活保護以外の選択肢…水際対策といわれ度々話題になりますが、不正受給を防ぐため仕方ない側面もあるのかな?と思います。
しかし、どうにもならないものはなりません。
強い意志をもって申請書類を受け取りましょう。
申請書類は複数あります。
- 生活保護申請書:氏名・住所・家族状況・扶養の有無・申請理由などを記入する。
- 収入・無収入申告書:世帯全員分の収入状況を申告する。
- 資産申告書:預貯金・現金・土地・生命保険などを申告する。
- 一時金支給申告書:住所不定の方が家を借りるために必要な費用を援助してもらうための申告書。
- 同意書:収入や資産について、福祉課や関係者に問い合わせなどの調査をすることの同意書。
申請に必要な物
印鑑・本人確認書類・預貯金通帳・保険証、年金手帳、年金証など・賃貸借契約書・公共料金の領収書など・給与明細・手当を受給している場合は受給を証明できる書類
世の中には不正受給を企む悪い人もいるので、生活保護の需給にはしっかりとした調査が必要です。
- 家庭訪問などの実地調査(生活状況の把握)
- 資産調査(預貯金・保険・不動産など)
- 扶養義務者による扶養の可否の調査
- 年金などの社会保障給付や労働収入などの調査
- 就労可能性の調査
調査期間は2週間程度で、長くても30日以内に結果が出ます。
生活保護が決定すると国民健康保険証は返却します。
保護費は毎月15日の支給で、受給中は毎月の収入状況の申告が必要です。
また、年数回ケースワーカー(福祉事務所の担当職員)の訪問があり、働くことが可能な場合は就労に向け助言や指導を受けます。
生活保護の代理申請はできる?
生活保護を代理申請することはできるのでしょうか?
生活保護の代理申請は可能です。
大前提として、受給する本人の「生活保護を受給したい」という意思が大切です。
困窮している場合や周りが強く勧めたとしても、本人が「申請をしない」「生活保護は受けたくない」など申請する意思がない場合は代理申請することはできません。
要需給者が、窓口に行けない申請書類に記入できない事情がある場合は代理申請が可能です。
代理申請できる人
- 要保護者の扶養義務者(夫婦・祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹)
- 要保護者と同居する親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の婚族
代理申請は誰でもできるというものではありません。
要保護者と同居する親族の場合、基本的には世帯全員の申請を代表しての申請となります。
また、【本人に生活保護を申請する意思があり申請書類に記入は出来るが窓口までいけない場合】は代理人ではなく使者として認識されます。
そのため、要保護者本人が記入済みの申請書類を窓口まで届けることは親族以外(民生委員・恋人・友人・知人など)でも可能です。
生活保護の申請書類を渡してもらえなかった場合
原則、福祉事務所の担当者が申請を拒絶することは申請権の侵害(違法)となるため出来ません。
しかし、何らかの理由で福祉事務所で申請書を受け取ることが出来なかった場合は、申請に必要な書類をインターネットからダウンロードすることができます。
また、法テラスなどで相談し福祉事務所まで弁護士に同行してもらうという方法もあります。



付き添える人がいる場合、同席してもらえれば心強いですね。
まとめ
この記事では、生活保護の申請は誰にでもできるのか?受給できる条件や申請方法について解説してきました。
生活保護の申請に躊躇してしまう気持ちはとてもよくわかります。
とても必要な制度ですが、国を頼るということに申し訳なさや情けなさを感じる人も多いですよね。
しかし、お金がないという状態は思っている以上に深刻です。
生活を立て直すため、自分のため、家族のためにも、生活保護の選択を諦めないで欲しいなと思います。